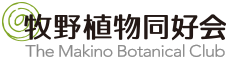研究会の記録
(MAKINO 第132号 p10より抜粋)
第843回 野外研究会 2025-03-25
22世紀の森づくり・神代
飯島和子(本会会員)
1.「22世紀の森づくり・神代」とは
「22世紀の森づくり・神代」(以下「22森」)は、「都市の森づくり」として100年をかけて武蔵野の雑木林を創ろう」というコンセプトのもと、2000年4月に東京都・都民ボランティア・有志企業の協働により発足したそうです。
場所は、神代植物公園東側拡張計画地域の一部で、1ヘクタールの平坦な草原に、国立天文台・味の素スタジアム・三鷹の森ジブリ美術館・多磨霊園の4箇所の道路拡幅工事や施設建設等で出た土を高低差3メートルに盛り土し、森としての原型を造ることからスタートしました。苗圃からの苗木育成および種子から育てた木を一本一本植えていくところから展開し、この「手作りの森」はまもなく活動開始から25年になるそうです。
2. 野外での観察
「22世紀の森づくり・神代」(以下「22森」)は、「都市の森づくり」として100年をかけて武蔵野の雑 10時 神代植物公園入り口前集合。天候は晴れ。参加者30人。
担当講師、係などを簡単に紹介後、「22森」会員の皆さんの案内で、観察地である「22世紀の森づくり・神代」の活動場所にむかいました。徒歩約20分で到着。…(以下略)
【当日の写真から:ケイオウザクラ】

研究会の記録
(MAKINO 第132号 pp11より抜粋)
第844回 野外研究会 2025-04-04
野川公園内の自然観察園(満開の桜観察)
永井 功(本会会員)
野川公園の前身は国際基督教大学のゴルフ場で起伏ある土地が広がり、自然樹形の樹木が何本も残っている。本日の講師は大石征夫先生、参加者20名。
1本立ちのヤマザクラ(❶)が満開、萼片は細いロート状、赤味を帯びた小さな新葉が開出していた。約100年ぶりに新種認定されたクマノザクラを含め、日本には10種(11種)の自生のサクラがあり、同種のサクラでも開花時期や形態に差異があり実生で育つ子孫が親の形質を受け継ぐ。挿し木で増えるソメイヨシノはクローンであり、全てが同形質で一斉に開花・満開となる。樹高の低いマメザクラが下向きで小ぶりな花を咲かせていた。来園者の通行や観賞の妨げにならぬように剪定され、蕊や萼の観察に適した高さの花は案外少なかった。
自然樹形を保ったエノキ(❷)の姿は凛々しい。多くの生き物に恩恵を与えており、蝶を例にあげればオオムラサキ、テングチョウ、カバマダラ、ヒオドシチョウの幼虫の食草となる。木の下の落ち葉を利用し幼虫や成虫の姿で越冬するものもいる。ただ、ここは根元に落ち葉がなくきれいにされており、蝶の冬越しも多難であるようだ。…(以下略)
【当日の写真から:ヤマザクラ】

研究会の記録
(MAKINO 第132号 p12-13より抜粋)
第845回 野外研究会 2025-05-16
前日光自然公園(横根高原の井戸湿原)
池田高信・飯島和子(いずれも本会会員)
日光国立公園の南側に隣接するのが前日光県立自然公園で、標高1373 mの横根山一帯に広がる眺望の良い高原が横根高原です。広い放牧場(前日光牧場)の草原、亜高山の森林、高層湿原(井戸高原)などの多様な環境の中で、多様な動植物を見ることができます。横根高原の標高1300 m付近にひっそりと広がるひょうたん形の湿原が井戸湿原で、湿原植物や周辺の亜高山植物など400種以上が生育する「植物の宝庫」といわれています。
8時に新宿駅前をバスが出発し、11時5分に、前日光ハイランドロッジに到着しました。
谷本𠀋夫先生が、いつもの笑顔で迎えて下さいました。山岳ガイドで先生の学生でもあった吉田さんが紹介され、元学生と思われる女性二人も加わりました。
前日光牧場では、6月から10月まで牛の預託を行っている放牧場とのことですが、シーズン前なので、残念ながら、牛を見ることはありませんでした。…(以下略)
【当日の写真から:トウゴクミツバツツジ】

研究会の記録
(MAKINO 第132号 p13-14より抜粋)
第846回 野外研究会 2025-06-09
洒水の滝
森 弦一(本会会員)
神奈川西部の植物に通じている講師の松岡輝宏さんのご案内で、何回か研究会を催している。今回は、山北町にある洒水の滝を訪れた。
洒水とは、仏教用語で「浄水を撒いて身や場所を清める儀式」のようで、そう聞くとなにやら厳かな気分になるかもしれない。案内板によれば、関東屈指の名瀑である、とあり、三段百二十メートル弱の流れが滝壺に注いでいる。観察会の目的は、もちろん名所観光ではなく、滝に向かう道沿いの植物、そして滝の周りに生える植物の観察にある。山北駅から往復6キロほどの道を歩く観察会である。(中略)
洒水の滝までは、御殿場線の線路を見下ろす道を歩くのだが、途中、一時騒がれたというシダ(国内初発見のイワダレヒトツバかと思われたが本来のイワダレヒトツバは国内に産せず、ビロウドシダとイワオモダカの雑種ヤツシロヒトツバ Pyrrosia ×nipponica ということになった;写真は栽培されていたもの)、そして桜並木にびっしり着生しているシダ(常緑のトキワシノブか)の説明があり、それから国道246号線を渡り、小田原方面に向かう県道726号に入る。洒水の滝は、この県道に沿った、向かって右手の山から流れ下る滝沢川の上流にある。…(以下略)
【当日の写真から:ヤツシロヒトツバ】